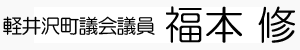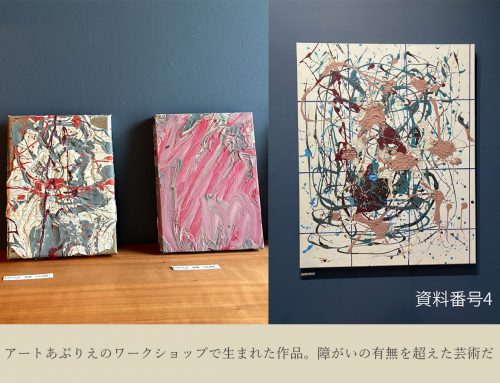軽井沢町議会令和6年6月第1回定例会での福本の一般質問です。
自然景観維持について、滞在型貸農園について、そして日本版DBSへの当町の対応について一般質問します。
自然景観維持について
開発のために樹木を伐採した場合、自然景観維持のために植栽を行うことが重要で、修景植栽の実行を町がしっかりと確認することが求められています。
開発した例として、例えば住宅地の一端に、写真にあるようなかなり広い土地が以前は雑木林のようになっていたところですけれども、皆伐された場所ですね。ここに限らず、町内あちらこちらに皆伐とか、ちょっと木は残っているけれども、ほぼほぼ全部切ってあるかなみたいな土地が散見されるのは、皆様お気づきのとおりかと思います。
令和4年9月会議における私の一般質問において、分譲等によって皆伐をした後、購入者が数年後に家を建てた場合、期間が空くことから植栽の確認に見落としがあるかもしれないという趣旨の答弁がありました。また、昨年12月の社会常任委員会において、開発地にて伐採した樹木に相当する植栽の実施チェックについての質問に対して、「見直しやチェック体制を検討したい」という趣旨の答弁がありました。そこで、どのような見直しが行われ、チェック体制が構築されたのかを伺います。まだ検討中の場合には、いつまでに検討を終えるのか伺います。
環境課長
修景植栽に関してのチェック体制についてですが、環境課では、現場へ出た際の確認のほか、3月に開催されました自然保護審議会において、伐採をされているような箇所があった際には連絡をいただくようお願いをし、各職員にも協力をお願いしております。
住民の皆様から、伐採に限らず植生に関する相談も寄せられておりますけれども、4月より植生学の専門職員を非常勤でありますが採用したことから、専門職員の助言も行っております。
また、6月会議再開に際しての町長の挨拶にもありましたとおり、チェックや監視ではありませんが、地域で植生に関しての助言やアドバイスを行えるような人材を育てていくための講座を9月開設に向けて準備をしております。このような地域人材を増やしていくことにより、地域ぐるみで自然を守る機運を高め、行政と連携して自然環境の保全と再生が進んでいくものと思っております。できることではありますが、少しずつ取り組んでおります。
ただ、課題も感じております。樹木を伐採後、事業者側の事情により中断してしまった場合、伐採後の状況で転売となってしまった場合など、新所有者には指導ができない案件もあり、事業が完了するまで現況のまま放置されている状況があることも事実でございます。
この伐採関係の課題も含めまして、自然保護対策要綱の運用に関し、時代変化とともに課題が洗い出されてきております。自然保護対策要綱の見直しに関する専門部会も設置いたしました。この委員会の中には法律の専門家もおりますので、様々な委員と議論を重ね、必要な改正につきましては、現時点におきましては、何をいつまでと具体的には答弁できる状況にありませんが、できることから随時行っていきたいと考えております。
以前の質問に対しての浮かび上がった課題、つまり開発後に期間を置いた後のチェック体制云々ということ、引き続き、今のご答弁でも問題意識として持っていらっしゃるということでございました。
そして自然保護対策要綱の見直しなども通じてということもありましたけれども、ただ、今の話の中ですと、その期間が空いたりとか、所有者が変わったりとか、そういった場合のチェックをどうするのかという解決策というのは、今ご発言いただいておりませんけれども、そのような見落としを解決するための手段としてはどのような考えをお持ちでしょうか。
環境課長
見落とし等の状況にもありますけれども、自然保護対策要綱に関係した土地利用行為の手続に関する条例に基づく環境課とは事前協議という形でやってきているんですが、事前協議で、その後、法律的な手続に入って、実際、事業の着手までかなりの時間を要する場合もあると思います。
現時点においては、事業完了したというものを事前協議の後、事業着手した、あるいは事業完了したというものの手続的なものがなくて、なかなかフォローアップというのは、今までできていなかった部分があると思います。
現在、土地利用行為の過去の台帳データもデータ化しておりまして、この後、GIS化もする予定をしております。GISに入れれば、フォローアップもできるというふうに思っております。GISにつきましては、令和3年度分までについては今年度まで、その後、4年、5年も随時やって、その後、GISの何らかのフォローアップできる体制をやっていきたいというふうに現時点においては考えております。
以上でございます。
事前協議のお話が出たのでちょっとお伺いしたいんですけれども、事前協議を経ないで行っている事業というものもあると思っておりますが、そのあたりの認識についてお伺いできますか。
環境課長
事前協議を経ないというものですけれども、当然、今後についてはいろいろな形で、私たちも現場に出て状況を見て協議がないもの、伐採に限らず、ほかの店舗開設などもありますけれども、そういった状況につきましては、職員、あるいは自然保護審議会の皆様から情報を寄せていただきまして、そういったものにつきましては、事後であっても手続をしてもらうよう指導をしていきたいというふうに思っております。
この事前協議を経ない事業については、関連することだと思いますが、テーマがずれてしまうので、あと1つを除いて質問しませんけれども、その残りの1つというのは、町としては事前協議を経ない、要するにルールを逸脱している人が得をするというようなことがないようなことを断固として指導していくと、そういうお考えであるということでよろしいですか。
環境課長
町におきましては、条例で手続というものがありますので、条例上の手続が必要なものにつきましては、当然周知もしていかなければいけないと思います。こういったものは手続をしてくださいというものも周知も併せまして、今後におきましては、そういったものをないよう私たちも監視の目を高めつつやっていきたいというふうに考えております。
軽井沢の魅力は何かというふうに問いますと、町民も観光客の方も、あるいは別荘所有者の方も、各種アンケートでは、自然が豊かなところが軽井沢の魅力なんだという答えがあります。軽井沢の名前の価値、ブランドというものの維持には、自然の維持というものが必須なわけです。これなくして、当町の経済も何も成り立たなくなっていくということかと思います。
そういった意味で、現在、自然保護対策要綱の見直しにも着手していらっしゃるということですけれども、この修景をちゃんとしたかという植栽の確認等は、当然樹木も寿命がありますから、切らなければいいというものではないということは、多くの方が理解していると思います。そういった意味で、木のライフサイクルを生かすということも、時には開発に伴う樹木の伐採には、そうした側面もあろうかと思いますが、いずれにしろ、開発自体は否定するものではありません。例えば住宅のために開発をする。それはなぜかといえば、当町に移住者が増えていて、前年対比で住民基本台帳の5月1日ベースで言うと、恐らく230人余り人口が増えているわけですけれども、将来的には人口減少というのが確実視されている現在ですので、軽井沢に移住してきてくださる方は歓迎すべき存在ですね。当然住むところも必要なので、開発も起こり得るということは理解しつつ、ただ、それと自然保護の両立をしっかりと図っていくという、このような重責を今、町が担っておられますので、担当各所におかれましては、今後ともしっかりと自然を守っていくという方向でお働きいただくことを期待して、この質問を終わります。
滞在型貸農園について
就農者の高齢化に伴い、今後、遊休農地が加速度的に増える懸念があります。遊休農地対策として、また長期滞在型旅客の誘客のためにも、滞在型貸農園、いわゆるクラインガルテンの整備について、町は令和6年度から令和7年度までの2か年で実施場所や需要調査等を行い、令和8年度にクラインガルテン構想を策定したいとしております。
事業の進捗状況はいかがですか。まだ進んでいないということであれば、令和7年度末までの具体的なタイムスケジュール、例えば実施場所の決定ですとか需要調査の時期についてお伺いします。
観光経済課長
今年度より検討を始めましたので、現段階では進捗状況をお知らせできるほどの状況ではございませんが、タイムスケジュールとしましては、まず本年度は農地として使用されておらず、事業が実施可能な場所の調査や、先行して取り組んでおられる自治体への視察を行いたいと考えております。その上で区画ごとに宿泊が可能なラウベと呼ばれる滞在型施設について、軽井沢の特殊性も考慮し、検討を行いたいと考えております。
来年度には需要についてのアンケートを行いまして、設置が可能であるとした場合には、遊休農地の対策の一環としまして、クラインガルテンの整備に向けたプロポーザルの仕様書の内容について検討を行いたいと考えております。
計画にのっとってやっているということですが、ただ、このクラインガルテン構想、土屋町長が町長選の際に掲げておられました滞在型保養文化都市という考えの一端を担うものなのかなと思っておりますけれども、そのような滞在型保養文化都市をつくるという町長を押した選挙民からすると、町政が発足して1年たった段階で、まだほとんど事実上構想が進んでいないということに関して、町長はこのスピード感についてどう考えるのかを伺います。
観光経済課長
重複しますが、まず今年度から令和7年度までの2か年で実施場所などの調査検討を行った上で、先ほど答弁させていただきましたとおり、今期の町長の任期中には、実現性の判断を行いまして、設置可能であると判断した場合には、令和8年度にプロポーザルを実施する予定でございます。
なお、事業化ということになりますと、用地の確保ですとか附帯施設の設置ですとか、費用も多額になろうかと思いますので、慎重に検討を行いたいと考えております。
以上です。
需要調査の方法についてお伺いいたします。
◎観光経済課長
アンケート調査を行いたい。クラインガルテンを設置した際にどのくらいのニーズがあるのか、利用者の意向を確認するため、春の緑のおたよりですとか、夏の風のおたより、あるいは町のホームページによるアンケートの実施を検討しています。
日本版DBSへの当町の対応について伺います。
2024年5月、子どもに接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用者が確認する学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律、いわゆる日本版DBSを導入する法案が衆議院特別委員会で可決されました。今後、法制化され、2027年に運用が開始されることが見込まれる状況になりました。そこで、当町においても今から法制化を見込んでの準備が必要であろうかと思います。まだ事実上未確定な部分ばかりかなとは思いますけれども、今後の検討にも資するであろうことから、現時点での方針等を伺いたいと思います。細かいことは、今は決まっていないというのは承知しております。
学校、保育施設、児童館における性犯罪事案の発生は当町でありますか。
こども教育課長
現時点における性犯罪の事案はございません。
過去にそういう事案がないということで安心しました。
学校、保育施設、児童館職員の性犯罪歴を法令にのっとり確認していくことは当然ですけれども、現在進められている部活動の地域移行に伴い、その指導者の性犯罪歴確認についてはどのように考えますか。
こども教育課長
現時点におきましては、確認方法に関する仕組みが確定しておりませんので、国の法整備や運用について注視し、対応してまいります。
国の方針が決まっていないからまだ考えていないというご趣旨の答弁と理解しましたけれども、質問しているのは、もちろん法制化も完全にはされていない状況ですから何も決まっていない、方針が示されていないということは明らかなわけです。それでも、あえて今、質問しているのは、町としての基本的な考え方ですね。自分として、町としてどう考えているのかというのがまずあって、法令ができたときに、それにのっとった対応をするのは明らかですけれども、法令でカバーしていないような部分に関しても、町として必要ならばそれを補うような施策を練っていくのではないか、練っていくことが必要なのではないかという趣旨で今、質問しております。
だから、まず自分たちの何が必要なのかということはしっかり考えていただく必要があるんじゃないかなという意味で質問しておりますので、決まってないからもちろは対応はできないから、対応が分からんというのは明らかなんですけれども、現時点である程度、こういう法律になるだろうというのは想定されているわけです。例えば今申し上げたような、部活動の地域移行の地域の指導者たちに対しての確認が町として必要と考えるかどうかという、その根っこの部分をどうなのかというのを今問うたわけですけれども、現時点ではまだ考えていらっしゃらないということなのでこれ以上質問しませんけれども。
ただ、町として、もう27年に施行される、運用されるということになるとそんなに時間ないので、今からそういう問題意識も持ってご検討いただくほうがよいと思いますし、そのきっかけになればというんで質問しております。
ちょっと同じような意味で、まだ示されていないからということだとそれで終わっちゃう質問なんですけれども、法律で義務化がされていない可能性が高い無認可保育施設の職員ですとか学習塾、文科系の教室、スポーツをしている団体の指導者の性犯罪歴の確認についてはどのようにお考えですか。
こども教育課長
福本議員おっしゃるとおり、性犯罪の部分につきましては当然認識はしております。最低限の部分等含めまして、国の基準等を併せまして実施してまいりたいと考えておりますが、現時点におきまして確認方法に関する仕組み、確定がしておりませんので、国の法整備や運用について注視してまいりたいと考えております。
すみません、併せまして、国の方針、先ほどの部分ですね。国の方針が決定しておらない部分もあるので、各事業所が適切に判断するもの考えております。
現在、法令化されておりませんので確たることは分からないわけですけれども、ただ、このままいきますと、恐らく先ほど言った無認可保育施設、学習塾等というのは義務化がされないという方向が見込まれるわけです。それを見込んでのご答弁なのか、ちょっと確認したいんですけれども、町としては特に監視をすることは考えていなくて、各事業所ベースで判断をしていくべきだというお考えが今あるということでよろしいですか。
◎こども教育課長
先ほども申し上げましたが、国の方針が決定しておりませんので、当然各事業所が適切にやってもらえるものと判断しているのが今現状であります。
質問は、先ほどもちょっと申し上げたことと重複しているんですけれども、町として何が正しいというような根っこのほうをしっかりとつくっていただいて、その法律が来たときにご対応いただきたいというのと、法律がカバーしていない部分で、町がここもカバーしなきゃいけないんじゃないかというような問題意識を持って準備をしていただく必要があると思っています。
いろいろ検討を重ねると時間もかかることかと思います。3年後には法律が施行されるとが見込まれるという中で、今から準備を進めていただきたいという問題提起にはなったかなと思うので、それでよしとしたいところではありますけれども。
あと1つ、私が懸念しているのは、この法律の運用が始まったときに、性犯罪歴の確認が法律で義務化されていない子どもに接する民間事業者については、任意で性犯罪歴の確認を求めることができるとする法律が想定されます。照会された人物に性犯罪歴があった場合には、事業者に先立って当該人物にまず連絡が先行して行くというふうな仕組みが想定されているわけですけれども、そうすると、先行して性犯罪歴があるということを当該人物が知る。知った段階で、自分に性犯罪歴がしっかり公に記録として残っているんだということを知って、応募を取り消すというケースも考えられるんじゃないかなと思います。
そうすると、事業者からするとそういう仕組みを当然知っていますから、照会をして、一定期間、そろそろ性犯罪歴があった場合には、その当該人物に対して国から連絡がある時期だなというふうな時期に応募辞退というようなことがあると、憶測として、事実は全く分からないんだけれども、性犯罪歴については本人が辞退した場合、事業者には伝わらないと思われていますけれども、その場合、当該人物が辞退したという事実から、あの人は性犯罪歴かあったから応募を辞退したんじゃないかみたいなことがうわさで出る、流布される危険性というのがちょっと懸念されます、私には。
それはなぜかというと、性犯罪歴みたいな確固たる個人情報に属することであれば、これは当然、秘密的なことだよというような認識が高まる。高まるというかお持ちかもしれないけれども、ちょっとしたうわさ話程度だったら、別にこれは大したことじゃないんじゃないかとか、そういうようなこともうわさされると、そういった応募して辞退したような人が、事実か事実じゃないのにかかわらず、そういったあらぬ、あらぬかどうか分からないけれども、うわさの流布によってちょっと苦しんでしまうというケースも想定されるなと思ったんです。
今、当然そんな細かいことまでの想定はしてないと思うんですけれども、それらを含めた個人情報の保護についてしっかりやっていく方針なのかどうか、ご想定お願いします。
こども教育課長
先ほどの質問の主旨がちょっと分かりかねますので、もう一度お願いしたいと思います。
文書で書いてない表現なんで、口頭で聞くとちょっと伝わりにくかったのかと思いますけれども、性犯罪歴という、すごい秘匿を有する情報に絡む法律が今後できてくると。そして、その情報を町の職員ではない事業者も触れ得ることに今後なってくることが見込まれています。
そういった個人情報の取扱いが、厳密に性犯罪歴とかそういう見て明らかな個人情報だけじゃない個人情報というものも、個人情報というか個人情報附帯情報みたいなものも今後、起こり得ると思っています。それは何かというのは、さっきちょっとるると申し上げて分かりにくくなってしまうと思うんで、また重複して言いませんけれども、いすれにしろ今後、性犯罪歴の確認というような新しい法律ができたことに伴って、新しい個人情報の取扱い方法というものが、細かいところまで目配りして考えていかなければいけないと思います。そのあたり、そのように目配りをしていく方向であるかどうかというのが質問の趣旨です。
こども教育課長
先ほども答弁いたしましたが、やはり国の判断基準のガイドライン等を踏まえまして、町としてもどうするべきことかというのは今後議論をするべきことだと考えております。また個人事業主についても、どのように周知していけばいいのかというのは今後議論していきたいと考えております。
以上です。
3年後の法制化ということで、油断しているともうすぐ始まってしまいますので、今から想定できることを問題点として洗い出して、法令に備えていただきたいと思います。
>> 当該一般質問速報